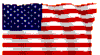|
◆幼年時代
1960年日本映画界に突如として彗星の如く登場し、新しい世代のスターとして衝撃を与えた加山雄三が、初めて楽器に出会ったのは8歳ときであったというから驚かされる。赤ん坊の時に、デキシーランド・ジャズやジョー・ダ二オルスのドラム・ソ口を子守唄に眠ったというエピソードも、今考えると、戦前の日本の家庭で、こうした音楽が溢れていたという、奇跡的ともいえる環境が、彼のオ能を豊かなものにさせた―因であったことを再認識させられる。
8歳になったある日、加山邸を訪問した親戚がオルガンを弾くのに興味をもち、それを弾く指使いだけをみてバイエルをこなすようになったという。中学入学後、近所の通学路の途中に、たまたまピアニストのレオ二―ド・クロイツァーが住んでいたことにより
(神奈川県茅ケ崎市在住の外国人は戦前の時代から多く、サザンオールスターズの曲タイトルにもなった"ラチエン通り"など在住した外国人にちなんだ地名などが現在でも残っている)、彼のピアノを毎日耳にできたという幸運にも恵まれた。加山はさっそく彼に師事することを志すが、結果としてはクロイツァー氏が推薦してくれた別の先生の指導を受けることになったという。ピアノのレッスンは正確な音感を養うのに大きな意味があったと推測されるが、加山雄三の場合は音楽とは直接関係のない趣味が、実は後に大ブームを巻き起こすシンガー・ソング・ライター、そしてギタリストとしての加山雄三という存在を形成するのに、大きな影響を与えたように感じられる。例えば、子供の頃から自宅のガレージの―角で楽しんだ、数々の素朴な発明や実験といったことや、自分で原動機付きのボートを製作したり、大好きな海で泳いだりダイヴィングしたりという、おそらく男性であればほとんどの人が、そのうちのひとつくらいは興味をもつ遊びを、彼は子供の頃から全て体験してしまっている。高校生になると、当時はほんの―部の人達しか楽しめなかったスキーも本格的にはじめて、国体に出場するほどだったという。彼の冒険心や持って生まれた才能といったものが、彼をとりまく環境によって―瞬の澱みもなく順調に伸びていったこと自体が、
もはや奇跡に近いといってよいだろう。
|

|
音楽はその人の心の動きや状態を、声や楽器によって表現することによって、他人に感動を与えるのだと思われるのだが、戦後生まれの若い世代にとって、加山のような少年期や青年時代を送ったスターは、まさに自分達の存在や主張の代弁者といった存在でもあったのではないだろうか?
加山が高校3年生に進級した頃、米国では映画「暴カ教室」のテーマ、「ロック・アランド・ザ・クロック」が、若い世代の圧倒的な支持を受けて全米No1ヒットを記録する。朝鮮戦争終了の平和ムードと戦争特需による好景気により、アメリカン,ドリームを享受するようになった米国に、突如として出現したテイーン・エイジヤーは、大人達にはまったく理解できない人生観と行動で非難の対象となったが、当時の彼らの心情を代弁したのが口ックン・ロ―ルであり、エルヴイス・プレスリーの衝撃的なデビューは時代の要求であったのかもしれない。米国のロックン・ロ―ルのムーブメントはFEN放送や映画によって日本にも飛び火して、米軍キャンプでカントリー&ウェスタンやジヤズを演奏していたミュージッシャンたちが、こぞってロックン,ロ―ルを演奏するようになり、結果として日本で口カビリ−ブームが起こる。この当時高校生だった加山は志賀高原の石の湯スキー場で、仲間が弾いたウクレレに興味をもつようになり、その後その友人の影響でギターも手にするようになったo(当時質屋で買った500円のギターで練習していたという)
◆ギター人生の始まり
大学に進学した加山は、同じ学校の仲間達と小遣い稼ぎのために"カントリ−クロップス"を結成する。加山はヴオーカルとサイドギターを担当したが、パンドのレパートリーはウェスタンとロカビリーがほとんどであったようだ。主な演奏場所は銀座の貸しダンス・ホールや学生パーテイー、米軍横田基地といったところで、この頃の加山の実体験が東宝入社後の"若大将シリース"のスクリ―ン上で見車に再現され興味深い。脚本を担当した田波靖男が、加山の学生時代のバンド体験を入念に取材したことが推察される。加山自身はこのバンド体験で、対人関係や社会性を身に付けたりすることができたと述懐している。また、パンドの練習場所は加山の自宅が多かったようだが、たまたま加山邸を訪間した加瀬邦彦氏(当時高校2年)が、その練習を見て音楽に興味を覚え、加山にギターの弾き方を教わることになった。氏の後のブルー・ジーンズやワイルドワンズにおける活躍は言うまでもない。
夏はヨットにダイビング、冬はスキー、お小遣い稼ぎにバンド活動と多忙な大学生活が終わろうとしていた頃、米国で50年代中盤に誕生したロックン・ロ―ルがひとつの転換期を迎えていた。全米ヒットがほぼロックン・ロ−ルに占領された頃はそのまま全盛が継続するかに思われたが、59年のバデイ・ホリーやリッチー・バレンスらの飛行機事故、エルヴイスの米国陸軍への入隊を契機に、次第に全米ヒットの曲に変化が見えるようになった。すなわちテイーン・エイジャー達の心を代弁してきた口ックが、商業的成功を収めたことによって、正規の音楽教育を受けた職業作家が書いた曲を大手出版社が抱えて、メジヤー・レーベルが用意したアイドル歌手が歌う、いわゆる"テイーン・ポップ、の時代が始まっていたのだ。そして全くそういった流れとは別に、カリフオルニア州のシアトルではボブ・ボーグルとドン・ウイルソンが、家族や知り会いのサポートにより初めてのシングル・レコードを制作、ギター・インストのアーテイストとしてインデイー・デビューを果たしている。これといった反応も無く1965年、日本に空前のエレキ・ブームを起こすべンチャーズのレコードデビューは静かなものとなったo
◆多重録音によるソング・ライテイング&サウンド・メイキング
1960年、加山が東宝映画に入社した頃は、米国で主流になりつつあったテイーン・ポップのヒットに日本語詞をつけて日本人歌手が歌うカヴアー・ポップの時代の創世期で、空前のエレキ・ブームやグループ・サウンズの大ブームの時代までこうしたポップ・ミュージックが意外に長く流行することになる。学生時代のカントリー・クロップスのバンド経験からポピュラー音楽を愛好した加山にも、―見、こうしたカヴアー・ポップ歌手のイメージがあるが、彼の音楽はあくまで米国の音楽を直接体験して、―切のフイルターを通さずに創造されているところが興味深い。
これを証明するのは、1962年に映画「日本―の若大将」の宣伝用に、サン出版でフォノシートとしてリリースされた、「ブルー・スウェードシューズ」や「グリーン・フイールズ」等の楽曲で、これらの―部が加山ひとりによる多重録音で制作されていることに驚かされる。
前年のデビュー・シングル「夜の太陽](東芝JP-1289)のような、プ口の作曲家による歌謡曲とは明らかに―線を画すが、1970年代に、例えば大瀧詠―によるナイアガラ・レーべルにおいて行われてたようなことを、それよりも10年以上前に発想して創造したアーテイストが、我国に存在していた事実は驚異としか言いようがない。そして、この多重録音の音楽を実際に聞いてみると、何か、加山が子供の頃から親しんだ自分流の発明遊びやコツコツとひとりで製作したボート作りの延長線上にこの音楽が存在しているように感じられる。後年、ランチャーズの喜多嶋修がインタビューで語ったように、「昔の茅ケ崎の子供達はギターもサーフ,ボードも自分で木を削って作ったものだ」という話も思い出される。話が前後してしまったが、映画「独立愚連隊西へ」でスクリーン・デビューを果たした加山は、翌61年、その代名詞ともなった若大将シリーズの第一作「大学の若大将」に出演して注目を浴びる。東宝の重役、藤本真澄プロデューサーが、戦前に制作された都会派コメデイー「大学の若旦那」の60年代版の制作を、当時は社員脚本家であった田波靖男に相談したことから生まれたアイデイアであったが、"若大将”という言葉は作家・黒岩重吾が、大阪の株屋時代に"北浜の若大将”と呼ばれていたことを新聞で知って、思いついたというエピソードが残っている。藤本/田波/笠原/杉江敏男監督のラインでスタートしたこのシリーズは 周知のとおり爆発的にヒッ卜を記録して、1981年、「帰ってきた若大将」まで制作される人気シリーズとなるが、映画の設定の中で加山が歌ったり、ギターを弾いたりするシーンがふんだんに盛り込まれていて、フアンとしては貴重な記録ともなっている。米国のエルヴイス主演の映画や英国のクリフ・リチヤード主演の映画にも共通する、我国を代表する青春映画といっても過言ではない。歌手デビユーと弾厚作の誕生若大将映画の主題歌、あるいは映画の挿入歌として数々のレコードがリリースされるが、はじめは職業作家による作品であったが、次第に、東宝文芸部で越路吹雪の歌の作詞や訳詞の仕事をしていた岩谷時子の歌詞に、加山自身のオリジナル・メロデイーをつけた作品が多くなる。弾厚作(加山のペンネーム)作品の初リリースは、65年6月の「恋は紅いバラ」であるが,これも映画「海の若大将」の中で歌われた曲であった。しかし、これより2年前の63年8月公開の「ハワイの若大将」にて、オリジナルの英語詩でこの曲は歌われている。加山が仕事の合間に弾いていたギターから、自然に生まれたメロデイーが、そのまま映画で使用され商業的ベースに乗ってしまったわけであるが、彼のヒット曲はこのタイプのものが実に多いように感じられる。こうしたことから、加山の音楽のもうひとつの側面は学生時代のカントリー・クロップスで体験した良い意味でのアマチュア・イズムであると考えられる。
◆初代ランチヤーズ結成
東宝入社後の61年に、東宝創立30周年の祝賀パーテイーのために、加山は藤本プロデューサーの命を受けて東宝の俳優仲間とバンドを結成している。ギター、ヴオーカルの加山と二瓶正也(ドラム)、津田
彰(ギター)、佐竹弘行(ベース)、白石剛敏(ぺダル・ステイール)というラインナップで、幅広いレパートリーを演奏したようだ。バンド名を、加山が好きな船が進水する(Lunch)という意味でザ・ランチヤーズと命名された。撮影の合間に曲を書き、ギターを弾いて、夜はバンド練習と多忙な毎日であったことが想像されるが、冷静に見つめるとこの時点で加山の本業はやはり俳優業であり、音楽はアマチュアもしくはその延長線上にあったことが重要なポイントといえる。
◆第二期ランチヤーズ結成
米国で60年に「Walk
Dont Run」が全米ヒットを記録して、波に乗るべンチャーズが63年にはヒット・アルバムを連発、彼らのエレキ・ギターによるビート・ミュージックに興味を覚えた加山は、文化放送で始った自分がパーソナリテイーを務める番組で、べンチヤーズの曲や自分のオリジナルのエレキ・サウンドを多数紹介するようになった。この番組をたまたま聞いていた母方の従兄弟で、まだ中学生であった喜多嶋修が加山邸を訪問、加山も若きべンチヤーズ・フアンの突然の来訪を喜び―緒にギターを弾くようになった。この出会いが修そして兄の喜多嶋瑛らと結成した第2期ランチヤーズへと発展してゆくことになる。1964年は"平凡パンチ"の創刊,東海道新幹線の開通、東京オリンピックの開催そして米国にビートルズが上陸するという年であったが、東京のエレキ・キダーを愛好する私立高校の生徒を中心としたサークル、東京インス卜ウルメンタル・サークル(TIC)が設立されたりして、まさに若者にとってゴールデン・シックステイーズを代表する年だったと言える。そしてこの年夏、アストロノウツの「太陽の彼方へ」が大ヒットを記録する。戦後生まれの若者が20歳の成人になろうとしていた時、フェンダーのソリッド・モデルによるリヴアーブ・サウンドが若い彼らのハートを揺さぶったのである。このヒットでスパイダースを脱退した、加山の愛弟子ともいえる加瀬邦彦が加入したブルー・ジーンズが、サーフインをテーマにしたアルバムを連発して注目を浴びる。
1965年正月、ついにベンチャーズが来日する。この衝撃の日本公演は、日本に空前のエレキ・ブームを巻き起こすことになるが、この年7月2度目の来日の際、加山雄三とランチャーズはフジTV"スターの広場"にてべンチャーズとの共演を果たす。この時の模様を記録したテープを聞くと、べンチャーズを前にやや緊張気味の加山の様子や、まだ高校生だった喜多嶋修の若さ溢れるギター・プレイが、今なお新鮮な感動をもって伝わってくる。この出演―週間前に完成したオリジナル、「ブラック・サンドビーチ」が披露されるが、不思議にレコードになったバージョンとは違った勢いや迫カがあって、今でもファンの間では話題となっているようだ。この曲を聴いて好きになったベンチャーズは、自分達の演奏によるシングル・レコードをリリースするほどだった。結果的にはべンチャーズがカヴァーしたことによって、世界中のエレキ・インストマニアの間でこの曲が知られることになったが、加山雄三という日本人が本来的に持ち得たオリジナルなセンスと、べンチャーズによってもたらされたコンボ・スタイルによるエレキ・バンドのビート感といったものが、実に魅力的にマッチングした名曲で、洋楽と邦楽の正当なる融合としては、六輔/八大による坂本 九の「スキヤキ」と双壁をなす存在といえるだろう。べンチャーズはその後、日本人歌手向けに数々のメロデイーを提供して、べンチャーズ歌謡のヒットを数多く記録するが、それ以前にそのべンチャーズ自体に、日本人のオリジナルが影響を与えた楽曲としても歴史的快挙と言える。べンチヤーズがもたらしたエレキが、日本の若者の精神空間に突如として侵入したことにより、空前のエレキ・ブームが起こることになるが、敏腕プロデューサーの藤本も当然ながらこの未曾有の大ブームを見逃さなかった。さっそく脚本を田波に依頼、「エレキの若大将」が制作される。
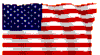
◆"エレキの若大将"誕生
1965年12月に公開されたこの映画の内容については、説明の必要が無いかと思われるが、当時、ぺンチャーズの日本公演を実際に見ることができた都市部の若者たち以外にとっては、この映画は都会のエレキ・ブームを手軽に楽しく体験できた唯―の存在であった。この映画によってエレキ・ブームが全国に飛び火、年が明けた66年の日本はまさにエレキ一色となってしまった。この映画の制作とほぼ同時進行で、加山は自分の従兄弟たちと結成していたランチャーズでアルバムを制作している。エレキ・ギターによるインストルメンタルと、英語詩によるヴォーカル曲だけで制作されたこのアルバムは、後に日本人によるポップ・ミュージックの草分けとして高い評価を受けることになるが、70年代日本のロックを創造したアーテイスト達が、まだほとんど少年期とはいえ強い影響を受けたアルバムとしても有名である。「恋は紅いバラ/Exciting
Sounds Of YuzoKayama」(日本コロンビアPS 1314-JC)というタイトルで発売されたこのアルバムの制作に、まだ高校生であった喜多嶋修も参加、早くも非凡な才能を見せている。そして、旧態然とした専属制度がまだ厳しかった日本のレコード会社において、洋楽レ−べルからレコードをリリ−スするという先駆的な例としても有名で、ブル―・コメッツが同じCBSレーべルから「青い瞳」の英語バージョンをリリース、同じ方式がGSブーム以降、日本ビクターのPhilipsテイチクのUnion、東芝のキャピトルで行われることになる。
このアルバムを今改めて聞き直してみると、加山という強烈な個性、空前のエレキ,ブーム、喜多嶋修という若い才能が有機的化学反応を起こし日本ではじめて誕生したポピュラー音楽の名盤であったことを再認識する。ほぼ同時期に、東芝より「ブラック・サンド・ビーチ」や「ヴァイオレット・スカイ」を収録したアルバム[加山雄
三のすべて/ランチャーズとともに」(T-7100)も発売されて、映画の主題歌のヒットとともに好セールスを記録する。まさに、加山にとってこの年はゴールデン・イヤーとなったが、1997年出版された田波靖男氏の自叙伝「映画が夢を語れたとき」の中で、加山自身より「あの頃僕は無我夢中でつっ走っていた、考えてみるとあれは30年先取りの物語だったんだなあ、今いろんなジャンルに若大将や青大将を見ることができる」という言葉が送られている。まさに日本全体がつっ走っていたあの当時、加山が残した音楽や映像は今なお、光を失わず輝き続けている。
1966年映画「エレキの若大将」の挿入歌「君といつまでも」が大ヒット、日劇における初のワンマンショーを記録した「歌う若大将」も公開され、その当時の人気ぶりが映像として残っている。ランチャーズをバックにエレキを演奏するシーンでは、当時慶応の学生バンド、プラネッツの堤光生、岩崎道夫らの姿も見れる。高校生だった喜多嶋修の大学受験等で彼らのサポートが必要とされたようだ。また、この年の夏、ブルー・ジーンズにいた加瀬邦彦が新しいグループを結成、加山にワイルド・ワンズと命名してもらうことになった。
加山はこの年のレコード大賞特別賞を受賞、NHK紅白歌合戦にも出場してその人気ぶりは最高潮に達していた。翌67年にはアルバム『加山雄三のすべて」の第2集、第3集が制作されるが、この頃になるとその音楽にも変化が見られるようになる。前年6月にビートルズが来日、べンチャーズがもたらしたエレキ・ブームも、10代を対象としたエレキ禁止命等の影響もあって、陰りが見えるようになり、代わって都会の大学生達によるフォーク、ソング・ブーム、そして67年2月デビューのタイガースに代表されるGSの大ブームがはじまっていた。欧米のロツクがサイケデリック・サウンドやアシッド・ロツク、プログレ等の方向を向くようになりR&Bのブームも広がりを見せてきたことにより、日本のポップ・ミュージックも変化せざるを得なくなっていた。67年4月、喜多嶋修が晴れて大学に入学、兄やクラス・メー卜らと第3期ランチヤーズを結成して、加山とは別の音楽活動も行うようになった。
1968年、東宝の若大将シリーズの脚本の全てを担当していた田波靖男がタイガースの映画「世界は僕らを待っている」の脚本を担当したが、この年はまさにGSの犬ブームが吹き荒れた年であった。
◆エレキ・ギターから離れた時代
1970年5月、加山は病気により母親を矢う。すでに若大将シリーズの映画の興行成績も下降線をたどっており、経営に参加していた会社の倒産なども重なって試練の時を迎えていた。しかし、美しき人生の伴侶を得て、再起を目指す加山の姿に静かに拍手を送るフアンも多かったようだ。
70年代の後半、東京の名画座映画館の深夜映画で、”若大将”シリーズでのリヴァイバル上映が話題になり、60年代の全盛期は子供だった大学生達が、こぞって深夜映画に足を運ぶ現象が見られるようになった。これは70年代初頭、米国における映画「アメリカン・グラフィテイ」の爆発的なヒットが日本にも飛び火して、60年代オールディーズのブームが影響していたようだ。このリヴァイバルで、他界した藤本プロデューサーへの花向けとして渡辺プ口社長、渡辺晋による「もう―度若大将を復活させる」という構想が急浮上、田波の脚本で「帰ってきた若大将」が1981年公開されることになる。
すでに、テレビ・ドラマやコンサートツアーで見事な復活を遂げていた加山による”田沼雄―。に、往年のファンが大喜びしたことは言うまでもない。この復活によって、60年代の音源が多数リイシューされるようになり、若いファンも全盛期の記録に親しむことができるようになった。
1986年にNHKテレビではじまった「加山雄三ショー」では、多彩なゲストが毎回出演して話題となったが、久しぶりに加瀬邦彦らワイルドワンズのメンバーをバックにエレキ・ギターを演奏する姿も見られるようになり、"エレキの若大将"の復活も予感させたのだった。そして長年二人三脚でアルバムを制作してきたプロデューサーが新しいレコード会社を設立したことにより、新レーべルにて加山の60年代作品の本格的復刻リリースが盛んに行われるようになった。入念なリマスタリングによって、往年の加山作品が新しい感動をもって蘇ることで、すでにレコードを持っている昔からのフアンも復刻CDを買いに走るという現象が起こった。90年代に入るとべンチャーズも見事な復活を遂げ、日本全国100箇所コンサートツアーを敢行、話題となった。1997年にはドラマーのメルテーラーが肺ガンのため亡くなった。
◆そしてハイパーランチャーズになった
子育ても終えた頃、(1994年2月頃)ワイルドワンズの島英二氏にまた昔のようにモズライトのギターを
弾いて「ベンチャーズごっこをやりましょう」と持ちかけられ数人のメンバーを集め、度々自宅で遊んでいた
ところ事務所の社長から「一度コンサートをやってみよう!」の一声で新高輪プリンス飛天の間でやったのが
きっかけである。1994年7月14日ハイパーランチャーズ正式デビュー!
|